AmazonLightsailのダウングレードに伴い、ほんの少しレイアウト修正した当ブログ。今回は改修箇所と、どういう理由で改修したかを語っていこうと思う。
トップページの動画を削除
改修前
当ブログのトップページには、そこそこ大きいサイズのフルワイド動画を配置していた。これはなんとなくお洒落じゃね?っていうくらいの適当な理由に基づくものであり、あんまり意思はなかったりする。まあ、ちょっと頑張ってる感は出てたんじゃなかろうか。
改修後
トップページの動画を削除し、最新記事とアクセス数が高い記事をリストで表示するようにした。
改修理由
ページサイズ及びストレージの圧縮。そもそも当ブログへのアクセスルートはだいたいの場合検索起因のため、トップページに遷移することは稀であった。そのため、トップページにこだわる必要なんてないと判断し、シンプルな構成にする事にした。
冷静に考えると、動画は情報価値を付けづらい。文字のない動画で視聴者にインパクトを残すのはプロでも至難な技だと思うし、それをただのシステムエンジニアがやるのは無理だ。そもそもブログのトップページで伝えたいことなんかねえのよ。
関連記事の削除
改修前
そのページの投稿カテゴリをもとに、同カテゴリの記事を表示していた。WordPressで作られたブログならだいたい入っているような気がする。
改修後
関連記事を削除。その代わり演算が必要なさそうなタグクラウドを配置。
改修理由
一つ目は、関連記事を使いこなせる状態ではなかったから。一般的な関連記事は、別にAIで作成されている訳ではなく、カテゴリorタグが同じものを指定の件数取得し、表示するというものである。
この場合、カテゴリ、タグ付けに意図があればこれでも精度の高い関連記事が表示できるが、当ブログのカテゴリは結構大雑把に切られており、関連記事(関連性はない)みたいな感じになっていた。
二つ目は、関連記事のパフォーマンスが気になったから。
実際の処理は読んでないし、あくまで自分で組むのならこうなるって話ではあるが、
①現在表示されている記事のカテゴリを取得
②同カテゴリ内の、自記事以外の記事を取得(ここが読めないポイント)
③関連記事を表示
みたいな感じだと思う。
このうち、②がなにをしているかによって、パフォーマンスが大きく変わる。単純に同カテゴリの最新5件を表示、とかであれば、パフォーマンスにはさほど影響はない。が、そんな単純な作りはしてないんじゃねえかって思ったので、分からないなら一旦外すか、となった次第。
コメント欄の復活
改修前
コメント欄なし。
改修後
コメント欄を表示。また、reCAPTCHAv3を導入。reCAPTCHAを信用し、メールアドレスなどのスパム防止用項目を必要としないようにした。
改修理由
もともと、現代はコメント欄がなくたってSNSでコミュニケーションが取れるというのが理由で、コメントを非表示にしていた。
しかし、snsでコメントを受け取った場合、直接それがブログに反映されるわけではなく、本当は存在していた疑問と、それに対する改善は見えづらくなってしまう。
そのため、変更履歴的な観点でコメント欄は有用なのではないかと思った。
ちなみに、自分はトータル15年ほどWordPressでブログを書いているが、コメント欄を表示していた事はほとんどない。あの頃ちょうどTwitterが流行り始めたくらいだしね。当時と比べたらTwitterで顔が見えない人とコミュニケーションする事もなくなったなあ。
とにかく、コミュニケーションの間口を広げる意味で、しばらくは置いてみようと思う。まあ現代のインターネットにおいては、いくら自分の情報を開示しなくて良かったとしても、ブログにコメント残すのはハードルが高い気がしてはいるが。
昔はリアルより気軽だったんだけどね。
最後に
今回はダウングレードに合わせていじった場所を理由付きで紹介してみた。正直なところ、このブログがどう変わったかなんて誰も興味がないと思う。
けれども、どうして変更したのかの考え方は、人によっては参考になるかも知れんと思ったので、書いてみることにした。
少なくとも何かを変えるには相応の理由が必要な訳で、それを伝えるってのは社会で生きるためにも必要な事だしね。
そろそろまた、後輩が増えるなあ。てか、俺今何年目だっけ?もう同期もいねえから分からねえや。しゃちょう、今度教えてくれ。
以上。
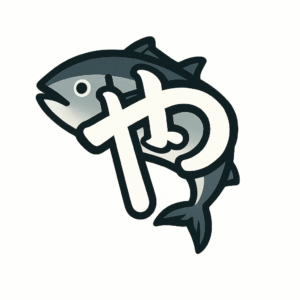
コメント